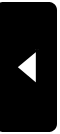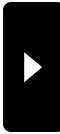災害ボランティアの方・・・名セリフをききました! 2024.02.10
能登半島地震での災害ボランティアの方が
インタビューを受けている放送をみました。
すると・・・
実に説得力のある名セリフといえる言葉で
話をされていました。。
「「何のお役にたいるかはわかりませんが無力ではない
と思うから、ボランティア活動をさせていただきます。」」
このような旨でした。

インタビューを受けている放送をみました。
すると・・・
実に説得力のある名セリフといえる言葉で
話をされていました。。
「「何のお役にたいるかはわかりませんが無力ではない
と思うから、ボランティア活動をさせていただきます。」」
このような旨でした。