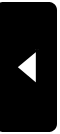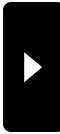2024夏山 乗鞍岳・剣ヶ峰へ登山道の緊の損傷個所を緊急再構築する作業へ 2024.06.27
2024年の夏山シーズン初めの7月に向けて・・・
最高峰の剣ヶ峰・・頂上小屋直前の登山道が流水などの影響から
損傷し崩れたと頂上小屋のオーナーからご一報を受けて。。
※ 緊急対応から早朝より現地ー・・・
まず゛は、変わらぬその雄姿はつぎの様子でした。




そして、剣ヶ峰の西方向の真横にある火口に沿って…大日岳が目前に・・
ある書籍から引用すると・・・「「乗鞍岳にあった幻の山岳すきー場」」
書籍には昭和9年から2戦後まで、大日岳から西方向に20キロ以上に
及ぶ尾根、全体からなすすきー場とのこと。。


また、登山道の改修+再構築すした区間、10m程度から北方向には・・飛騨山脈の槍ヶ岳などの稜線
がクッキリと望むことができました。

●●なお、登山道では路肩を現地の石で積み上げ作業と歩くところを石張り・・石畳みとして構築をしました。。